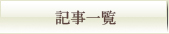- Aug.21
2016 - 第20回企画特別部会の報告
- Aug.21
2016 - 国立大学協会からの提言
平成32年度(2020年度)から実施予定の「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」における国語系記述式試験について、国立大学協会から8月19日に提言が出されました。
記述式試験の採点は時間がかかってしまうため、これまでは別日程での実施が検討されていました。それを同時期に実施するために出願先の各大学が採点を行うことを提案するという内容です。
詳細は国立大学協会のサイトをご覧ください。
- Aug.03
2016 - 第19回企画特別部会の報告
文科省で行われた第19回教育課程企画特別部会の記録を載せました。ご参考にどうぞ。
議事概要
今回公表された資料の中に、科目構成と標準単位数に関する項目がありました。これについて配布資料の一部は以下の通りです。
高等学校の各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数(イメージ)
- Jul.12
2016 - 第18回企画特別部会の報告
- Jun.28
2016 - 第17回企画特別部会の報告
- Jun.27
2016 - 第5回高等学校部会の報告
- Jun.21
2016 - 第10回外国語WGの報告
- Jun.16
2016 - 第4回高等学校部会の報告
- Jun.02
2016 - 第3回高等学校部会の報告
文科省で行われた第3回高等学校部会の記録を載せました。ご参考にどうぞ。
議事概要
今回は科目の構成に関する議題があり、配布資料の一部は以下の通りです。
現行の科目構成・新科目構成案・国語の見直しについて・地歴公民の見直しについて
- May.31
2016 - 第9回外国語WG及び第5回理数探究WGの報告
文科省で行われた新課程のための第9回外国語ワーキンググループ及び第5回高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方に関する特別チームの記録を載せました。ご参考にどうぞ。
第9回外国語WG議事概要
第5回理数探究WG議事概要
※新科目の名称はこれまで「数理探究(仮称)」とされていましたが、現在は修正され「理数探究(仮称)」として検討されています。