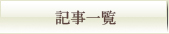- Jan.09
2010 - Linkリスト
- Dec.23
2009 - 受験数学の理論問題集「数と式」の発売日詳細
ある程度詳しくわかりましたので、報告します。12月25日から全国の書店に送り出します。ですので、土日の配送があれば、26日ですが、ない場合は一部の地域を除いて28日ころに到着し、そこから書店に並びます。
ちなみに都内の駿台の校舎には25日くらいから並ぶかもしれません。
- Dec.22
2009 - 受験数学の理論問題集「数と式」の発売について
私のところにはすでに完成品が届いていますが、この本の奥付には2010年1月9日とあります。しかし、駿台文庫のHPには、12月29日とあります。正確なところはわかっていないので、この2つの日付を書いておきます。
今回は、入門者と高3生のようなある程度学習した人にも使えるようにと考えているので、結構厚いです。高1のときから高3のときまでの長い間使えるようなものとして作りました。
- Dec.17
2009 - 関西は熱い
13日に日帰りで駿台の教育研究セミナーで関西大学まで行ってきました。教育研究セミナーというのは、高校の先生を対象に教授法などを講義するものですが、92名が集まり、今までの中でもっとも質問等も多く受講者から熱意を感じるものでした。
受験生はもとより、教育者の方々にもお役に立てるようこれからも励んでいきたいと思います。
- Dec.16
2009 - 整理
立場が変わると発言が変わるというのは、普通のことでしょう。ただ、それが急すぎるとちょっと戸惑うこともあります。
私は、知り合いの国会議員は30名ほどいますが、その半分以上は新人議員、復活議員です。当選前には普通に「この国を一緒によくしていきましょう。」とか 「協力お願いします。」などと言っていましたが、いざ、当選してしまうと急に態度が横柄になってしまう人が多いのは大変残念です。確かに国会議員という高 い地位は得たのかもしれませんが、人間の中味は変わっていないはずなのですが。
先月私が会った国会議員も選挙運動中は笑顔を振舞っていましたが、1対1で会ったときはヤクザより怖く、なめた態度で接してきました。その直後、テレビカメラがまわると劇的に「いい人」に変化しました。みなさんは普段の国会議員の顔を見たことがありますか?
また、子供手当ての話もありますが最近は「騙された」と思っている人も多いのではないでしょうか。
1対1で会っているときは、ポスターの笑顔はどこへ行ったの? と言いたくもなりました。
ということで、来年は少し関係を整理しておこうと思っています。重要な政策を考えてもらえる人だけいればよいと思ってきました。
来年はメディア、および一般書としての新書の執筆などもあります。私は、生まれながらに悪い人間はいないと考えていて、育っていく環境の中で不幸な状況に 出会い少しずつねじれていくのだと思っています。これは、大人になってからも(ねじれるのは)起こることがあります。
国会議員の様子を見ていると、子供達に悪影響のあるものも多くあり、そのような内容も伝えたいと思っています。
- Dec.05
2009 - 受験数学の理論「数と式」の刊行について
すでに、すべての原稿を提出し印刷を待つだけですが、おそらく12月20日過ぎに書店に並ぶのではないかと思います。
今はその続編(「図形と式・ベクトル」)を書いています。
- Nov.23
2009 - 受験数学の理論「数と式」の情報
大変お待たせしていますが、受験数学の理論問題集「数と式」のプチ情報を少しだけ。
第1章 数式の基本 例題 16 題、基本演習 42 題
第2章 方程式の解法とその応用 例題 12 題、基本演習 31 題
第3章 不等式の解法 例題 8 題、基本演習 20 題
第4章 不等式の証明とその応用 例題 5 題、基本演習 16 題
第5章 整数 例題 13 題、基本演習 43 題
こんな感じです。
よくある話ですが、このシリーズを知らない人は、「えっ! 例題って、これだけしか問題がないの」とか思うようですが、例題にはいろいろと凝縮されています。そして、見たことはない人は100ページくらいの薄さの 問題集を想像するようですが、持っている人は知っている通り、自学できるような解説なので本編と解答解説をあわせると400ページを超えます。よくある例 題とその解答あわせて1ページではなく、例題1題につき解答は2〜4ページです。
今回は、高校数学習いたての人から、受験を間近にひかえた高校3年生も使うことを想定したため両者の要求を満たすようにしてかなり苦労しました。
あとがきは書き直しました。
- Nov.17
2009 - お知らせ
現代数学社という出版社があります。ここから毎月「理系への数学」という雑誌が刊行されていますが、今月号(12月号) の裏表紙をめくってみてください。
何が書いてあるかはお楽しみ。
- Nov.10
2009 - 告知事項
「幸せ物語」の書籍版は 2 巻構成ですが、1 巻はただいま印刷中です。また、受験数学の理論問題集「数と式」についてはもうすぐ発売日を公表できるかなと思っています。
この他、冬期講習・直前講習のテキストと駿台教育研究所のテキスト等を並行していて忙しい状態で、なかなかメールの返事ができずにメールをくれた人にはすいません。
また、ただいま執筆中で授業配布の「幸せ物語」については、期限限定でここでアップしていこうと思っています。
- Sep.22
2009 - 東大実戦
もう有名な話なのかもしれませんが、東大実戦の成績優秀者で理IIで227点、数学で94点のところに駿台のある先生の名前をもじってペーネームで受け ている(らしい)人がいます。過去にもいました。でもそういう人って、成績優秀者に名前を載せる自信があるからするんでしょうね。びっくり。